過去1年の記事ランキング
今日頭の中で流れていた曲 ~誰かこの曲を止めてくれ!!~ Republica(イングランド) - Ready to Go
今日頭の中で流れていた曲 ~誰かこの曲を止めてくれ!!~ Republica(イングランド) - Ready to Go 確か97年くらいに購入した多分UKとかそっちの方のヒット曲コンピChart Bustersに収録されてたこの曲。 このバンドは1994年結成で、96から98年あたりが絶頂期だったそうな。 ジャンルは”テクノポップ パンク ロック”とか、Melody Maker(音楽系新聞か何か)には”エレクトロニカ”とかいわれていますけど、ジャンルわけって難しいね。 彼らのファーストアルバムRepublicaはアルバムチャートで4位を記録。セカンドアルバムSpeed BalladsとそのリードシングルFrom Rush Hour WIth Loveはそれぞれ37位、20位だったそうです。 その後レコードレーベルがBMGに吸収され、Best Ofが発売、しかしヴォーカルのSaffronは彼女の新しいバンドのウェブサイトから「ファンの皆様へ、このまがい物のリリースにだまされないで。これはまったく公式なものではなくて、バンドはこれに関する取引をしてないし、この話も聞かされてすらいなかった。収録曲も私たちが選んだものじゃないし、カバーの写真もずいぶん昔のもの、クオリティーも悪いし、バンドが新たなアルバムを作るために何の貢献にもならないわ。」と述べたそうな。 その後彼らは新たなリリースもなく、メンバーもソロでやってたり。 ヴォーカルの人はナイジェリア生まれで、ポルトガル、中国、イングランドから血を引いてるんだって。 彼女はThe Prodigy(イングランド)のFuel My Fireでfeatヴォーカルしてるよ。 Junkie XL (オランダ)のアルバムでも歌ってるみたい。 では肝心の私の頭の中の曲 Republica - Ready To Go (Pop Version) Ready to Go の後のヒット曲 Drop Dead Gorgeousもどうぞ。 この曲は映画スクリームの劇中でも使われてるけどサントラには残念ながら入っていません。残念・・・。 Republica - Drop Dead Gorgeous じゃあおさらいで、だいぶクールになってZoom Zoom Zoomな、US版。 Republica - Ready To Go (U.S. mix/r...
Moulin Rouge - 『Boys Don't Cry』日本語版も大ヒットのスロベニアのハイエナジーグループ
Moulin Rouge(スロベニア)は、ヴォーカルのAlenka Šmidová-Čenováとソングライター、キーボード、プロデューサーを兼ねているMatjaž Kosiからなるグループ。名前はもちろんあの映画にもなったフランスのキャバレーからきている。 元々はVideosex(当時はスロベニアじゃなくユーゴスラビア)とシンセポップグループにいたMatjaž Kosiがバンドを脱退し作ったのが、Moulin Rouge。バンド設立の1985年当時は3人の男性からなるバンドだったのだが、ヴォーカルのAlenkaとMatjažとの二人バンドになるのは1987年のこと。1988年にはユーロビジョンに向けたユーゴスラビアの国内予選で「Johnny je moj」が5位となっている。その後1990年まではアルバムを出していたものの、一時活動を停止していたのか、2000年にはバンド名を「Moulin Rouge 2010」と改め、Matjažと新たなボーカルKarmen Plazarで活動再開したようだ。 Wikipediaの解説ではこのバンドは「ドイツ、スカンジナビア、アメリカ、イタリア、そして特に日本のエレクトリックダンスミュージックファンのあいだで成功を収めた」とされている。 国際的にヒットしたのは1987年の「High Energy Boy」と、1988年の「Boys Don't Cry」。 アルバムタイトルにもなっている「Boys Don't Cry」を聞いたときは Stock Aitken Waterman (UKのプロデューサーチーム。以下SAW)がプロデュースしてるのかと思った。それくらいSAW的で楽しい感じが好きで、そしてヨーロッパ訛りの英語に萌える人にはたまらないかもしれない。 だが私にとっては楽しいだけのメロディーはつまらない。なので言っちゃ悪いが、「その程度」かと思ったのだ。しかし!他の曲を聞いてみると、ただ「SAWっぽい」だけではないことがわかってきた。と共に、彼らの音楽の面白さに気づいた。
Tuesday Girls - When You're A Tuesday Girl ノルウェー
“メンバー全員全員火曜日生まれだから” という安直なネーミングの安直なネーミングの謎の5人組ガールバンドTuesday Girls。 音楽版ウィキペディアといった感じのするLast.fmですら特にこれと言った情報も(リスナーも)無い。日本版CDでは日本でのプロモーション時の写真がどかどか載っているので下手すると日本でしか流行らなかったのか、はたまたすぐに解散、もしくは別名で活動か。 元気の出るポップと言ったところか。楽曲は結構良い。元気を出したいときにいいかも。 なぜかアマゾンにはシングル、“いい子になれなくて”と、ノルウェー公演版とカラオケ版収録の“ライト・バイ・ユア・サイド ”が売られていた形跡が。(どちらとも持ってないけど) ノルウェーの、悪く言えば普通のポップバンドで、しかも楽曲が特にヨーロッパ的でないこのグループがシングルを2枚も発売、その上アマゾンでも売られていたのかと思うとやはり日本市場狙いだったのか。
『ミッション:インポッシブル/ローグ・ネイション』の予告編のあの曲は?
『スパイ大作戦』の映画版シリーズ最新作『ミッション:インポッシブル/ローグ・ネイション』の予告編に印象的に使用されている曲をご紹介。 この曲「Ready or Not」はThe Fugees(アメリカ)というヒップホップグループによるもの。ラッパーのWyclef Jean、R&B歌手として有名なLauryn Hillなどがメンバー。 曲はUK Singlesで1位、アイルランドとフィンランドのチャートで2位、スウェーデンとオランダで3位となっている。 彼らのセカンドアルバム『The Score』に収録されている。 『ミッション:インポッシブル/ローグ・ネイション』版の「Rogue Nation Mix」はこちら。 ( abcxyz )
Rebecca Black(アメリカ) 史上最低の曲「Friday」を歌う13歳
Rebecca Black(アメリカ) 史上最低の曲「Friday」を歌う13歳 獣医の夫婦のもとに1997年に生まれたRebecca Black。学校では優秀で、ダンスを習ったり音楽のサマーキャンプなどにも参加。2008年愛国NPO教育団体「Celebration USA」に参加後、公の場で歌い始める。この時点ではSelena Gomez(アメリカ)やJustin Bieber(カナダ)が好きな普通の10代の子だった。 2010年末、BlackはクラスメイトにLAのレーベル、Ark Music Factoryでミュージックビデオを作れると教えてもらい、ミュージックビデオをプロデュースしてもらうことに。母親が4000ドル(約34万円)を払い、ビデオの所有権をArk MusicではなくBlackが握ることに(この権利分だけで2000ドルしている)。 2011年2月10日YouTubeとiTunesで「Friday」をリリース。その後バイラル効果でビューがドンドンと増えていき、デジタル版シングルの初秋売り上げは4万コピー。3月25日にパブリシストとマネージャーを雇ったそうな。色々なソングライターやレコードレーベルからアルバム制作の提案をうけているとのこと。現在は新曲「LOL」(Laugh Out Loud/大声で笑うの略日本で言うと「w」みたいな意味)を録音中だとか。 では早速話題の「Friday」をどうぞ。 * パラパラ漫画を再現しようとして失敗した感のある部分が後半にあり、「強い光が点滅」的効果のあるパートになっているので注意。なお、該当部分を「SEIZURE TIME!」(発作タイム!)とネタにしたり、「Friday」部分を「Fried Egg」(玉子焼き)と空耳してみたり、ペドベアーが出てきたりもする 「Memes Mash-up」バージョン なんてのも作られている。 お聴きのとおり、というか、まあ、結局のところ「史上最低の曲」として有名になってしまった「Friday」。あのJustin Bieber(カナダ)の「Baby」よりもYouTube上で嫌われた曲となっている。(「Baby」は現在121万以上の低評価、60万の高評価、対する「Friday」は、現在170万以上低評価、高評価は21万程度。) だがこの曲を評価して...
音楽ファン必見、映画『ベイビー・ドライバー』を観る前に聴いておくべき曲&元ネタ紹介!
日本では8月19日公開予定の映画『ベイビー・ドライバー』、一足お先にフィンランドで観てきました。 映画としては「歌わないミュージカル」といっても良いほどに、使用される楽曲と映像とが深く関連づけられた作品ともなっています。テレビシリーズ『SPACED 〜俺たちルームシェアリング〜』、映画『ショーン・オブ・ザ・デッド』、『ホットファズ』などで知られるエドガー・ライト監督は、非常にテンポ良く映像をカットする作風でも知られているんですが、それが極まった感じの作品でした。ただ、作品の内容的にはある意味「大作映画っぽい」感じで、ライト監督の持つ趣味性とか毒とかが抜かれた大味になった感も否めませんが、それでも爽快感溢れる素晴らしい娯楽作品であることには変わりありません。それにこれから他のエドガー・ライト作品を観るという方にはうってつけの作品だと思います。 まずは予告編をご覧ください。予告編にも何種類かありますが、この映画を一番よく表しているのは多分この「Tequila」予告編! 動画は Sony Pictures Entertainment より。 そんな『ベイビー・ドライバー』で、主人公が常にiPodで聴いている音楽も作品の一つのキャラクターであるといえます。今回はそんな本作の音楽や元ネタになった曲をご紹介。映画公開前にこれらの曲を知っておくと、さらに映画が楽しめること請け合いです。各曲の紹介には各アーティストのアルバムなどもご紹介している他、最後には今回紹介した全曲が収録された映画のアルバム『Baby Driver (Music From The Motion Picture)』も掲載しています。 Jon Spencer Blues Explosion(アメリカ)によるノリノリの「Bellbottoms」。 動画は ripoffrecords1 より。映画冒頭の強盗で使われるノリノリの曲です。 印象的な出だしは誰もが聴いたことのあるBob & Earl(アメリカ)の「Harlem Shuffle」。音楽にあわせてコーヒーを買いに行くベイビーの聴いている曲。ある意味映画が一番ミュージカル的な瞬間を飾るシーンで使われた曲です。 動画は dalkey130388 より。 The Damned(イングラン...
Late Night Alumni(アメリカ) まとめ
可愛らしく、甘く囁き系の歌声にちょっとダンステイストが入ったアメリカのグループLate Night Alumniをご紹介。歌い方に好き嫌いが別れるところかもしれないが、Lykke Liの歌い方がいけるひと、好きな人はハマれるかもしれない。 ---------- 結成~ファーストアルバム 『Empty Streets』 2003年、Finn Bjansonが数曲プロデュースした地方のクリスマスCDを聴き、Becky Jean Williamsの声に美しい声とスタイルに感銘を受け、「Empty Street」を作ることとなる。FinnはすでにKaskade(アメリカ)ことRyan Raddonと共に働いていたこともあり、Finn、Kaskade、BeckyでLate Night Alumniを結成。2004年にHed Kandiからフルアルバム制作のオファーを受ける。まだなにか足りないと感じていたFinnが、「一緒に働くきっかけを何年も探していた」というプロデューサー、John Hancock(命名はアメリカ独立宣言に署名した ジョン・ハンコック から取られているとか)を加え、ファーストアルバム『Empty Streets』が完成する。発売の2005年はHed KandiがMinistry of Soundに買収された時期と重なったため、レーベルからのサポートは得られなかったものの、人気を博した。 シングル「Empty Streets」はUKでトップ10ラジオプレイに選ばれ、スペインでは1位を記録。トヨタのコンパクトカー、「iQ」の コマーシャル にも同曲が使われた。曲名通り、人通りも車通りもないストリートをiQで走り抜けるコマーシャルとなっている。その映画『ブレードランナー』にも似た偽物の日本の姿が癪にさわったから作成された…なんてわけではないだろうが、日本の電車から撮影されたものと思わしき美しい映像にあわせて「Empty Streets」が流れるものがあったのでどうぞ。 『Empty Streets』 こちらの版はレーベルが「Hed Kandi」となっている。 日本版タイトルは『レイト・ナイト・アラムナイ』となっている。右はiTunesでの視聴/購入用リンクだ。 iTunes版のレーベルは「Quiet City...
観る前に聴けば映画『アトミック・ブロンド』が倍楽しめる80年代洋楽集
シャーリーズ・セロン主演のハードコアなアクション映画『アトミック・ブロンド』。1989年のベルリン崩壊前後を背景に、スパイ達の活躍を描いた映画。予告編で使われるNew Orderの「Blue Monday」(83年版)が印象的だが、本編収録曲も当時流行った曲ばかり。作中で流れる曲が、ただの映画の背景音楽ではなく、「映画作中の人がシーンの最中に聴いている音楽」となっているところも面白い。 時代背景や音楽を知らなくても楽しめる映画だが、 前回紹介した映画『ベイビー・ドライバー』と同じく 、使われる楽曲を知っているとさらに楽しめるはず。まずは予告編から。 動画は Universal Pictures より。 なお、映画音楽はタイラー・ベイツ(Tyler Bates)が担当。本作監督のデヴィッド・リーチ(David Leitch)の前作である『ジョン・ウィック』、ジェームズ・ガン(James Gunn)監督の『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズや『スリザー』などでも音楽を担当している他、ザック・スナイダー(Zack Snyder)監督作品『ドーン・オブ・ザ・デッド』、『300』、そして本作と同じく80年代の名曲がたくさん流れる『ウォッチメン』でも音楽を担当している。 紹介楽曲 ・New Order・Health -「Blue Monday」 ・Depeche Mode -「Behind the Wheel」 ・Queen & David Bowie -「Under Pressure」 ・David Bowie -「Cat People (Putting Out the Fire)」 ・Peter Schilling -「Major Tom (Völlig Losgelöst)」 ・Nena・Kaleida -「99 Luftballons」 ・George Michael -「Father Figure」 ・After the Fire・Falco -「Der Commissar」 ・Siouxsie and the Banshees -「Cities in Dust」 ・Re-Flex -「The Politics of Dancing」 ・Marilyn Manson & Tyler Bates...
『イングリッシュ・モンスターの最強英語術』書評と、もっといい勉強方法。
イングリッシュ・モンスターの最強英語術 菊池 健彦 著 ひきこもり生活 のなかで英語を勉強(これを「ひきこもり留学」と表現しているが、私はナカミを読むまでひきこもり者が留学した話なのかと思っていた)、 TOEIC990点満点 を24回もとったという著者の英語学習法を記した本。 1章:まず読むべきは著者が如何にして英語勉強、そして上達に至ったかを記したこの章だ。そしてそれは多くの英語学習者、引きこもりの人々に 希望を与える であろう。 2章:「日本人は英語が苦手」という私たちに 植えつけられた認識を考え直す 役に立つ。 3章:この章に書かれていることは正論すぎて、読んでやる気を無くす人もいるだろう。 やる気を無くしそうになった方はぜひこの投稿を最期まで読んでほしい。 ちなみに、ニュージーランドにある大学の外国人向け英語学習コースでは1日5単語程度が記憶可能な単語数だとしている。 4章:英語のテレビ番組などを通じて聞き取りを学ぼうとし挫折しかけた人にはいいかもしれない。 5章:写真付きで紹介されるDIYアイテムには引いてしまう人も多いかもしれないが、ナイスアイデアだ。私の通っていた大学の英語の先生はテープレコーダーを使ってこれと同じことをしていた。ただ、個人的には自分の発音をわざわざ聞き返さなくても真似るだけ、もしくはシャドーイング、で十分だと思う。もちろんカタカナ発音の英語を完全に取り払えることが出来ればの話だが。 6章:章のタイトル「 文法なんてだんだん慣れるもの 」にはまったくもって納得。SVOやSVCなんて実際に英語を使う上で必要ないどころか変に知っていてもじゃまだと思うのでこの章自体読み飛ばしちゃってもいいんじゃないかとも思う。 7章:TOEICを受ける人なら読んで損はない。 8章:「読み飛ばして構わない」と名が打たれているが、意義があることが書いてある。 一読に値する本だと思った。これから英語を勉強しようという人にはぜひ読んでもらいたい。 だが、彼の実践した勉強方は、なかなかの モチベーション がないとやっていけないはずだ。そこでここに私が実践してきた英語勉強方を記す。そして、それが多くの英語、語学学習者の助けになればとも思う。 -------------------- 私abcxyz自身もまた、引き...

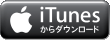
コメント
コメントを投稿